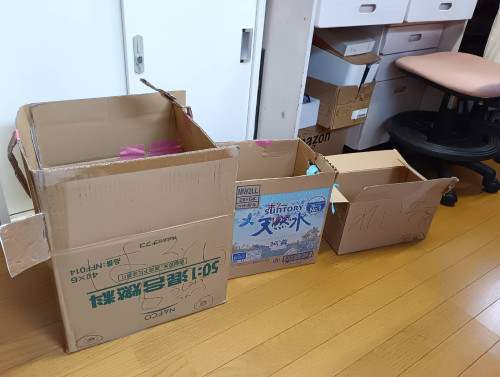ブログ
2025-07-15 13:13:00
2024年度総会
2025年7月12日にNPO法人月と太陽の総会を行いました。
第一部の活動報告では、スタッフが一年間を振り返って、子どもたちの成長した様子をそれぞれに発表しました。
第二部では理事、監事より、NPOや、児童発達支援、放課後デイサービスについてお話をしていただくなど
とても有意義な総会となりました。
2025-07-04 11:23:00
good デザイン
2025-06-24 13:34:00
作物と子育て
2025-06-19 11:18:00
桑の実とブラックベリー
2025-06-10 14:21:00
続 駄菓子屋ほしのこ
駄菓子屋ほしのこがオープンしてから一ヶ月が経ちました。
お金の使い方を学んでいる子供達です。
一所懸命に考えて予算内で使う子。
まだまだお腹はすいているけど、我慢して買わない子。
ほしのこ銀行から借り入れして限度額目いっぱい買って食べる子。
お友達が買った物なのか、自分が買った物なのか分からなくて困ってしまっている子。
子供達の性格が見えてきて面白いな~と思っています